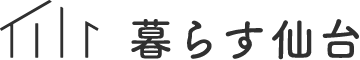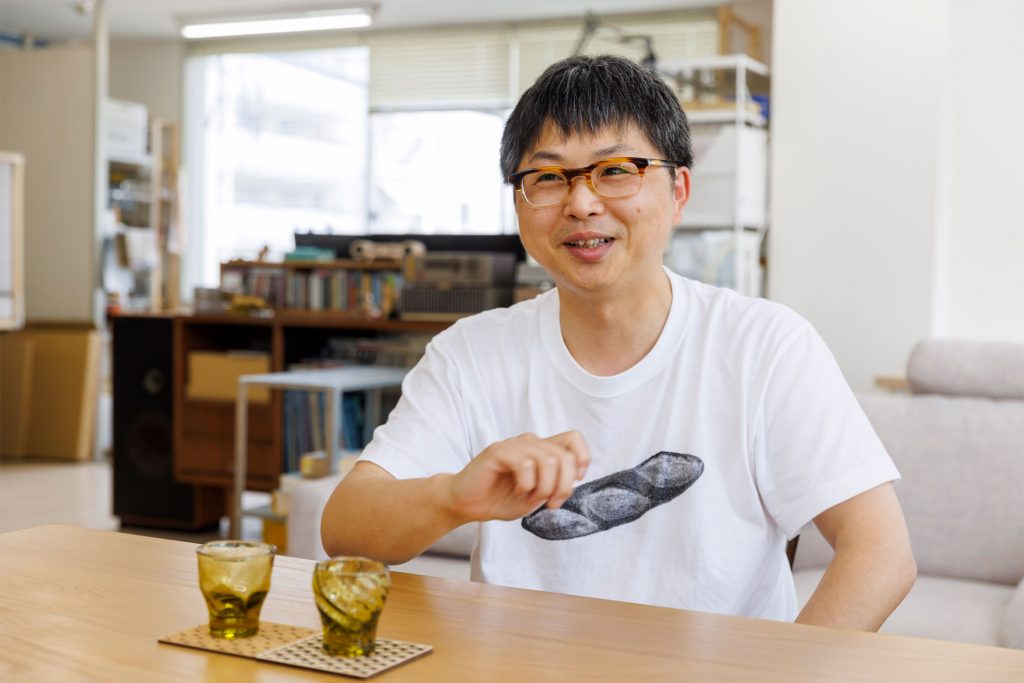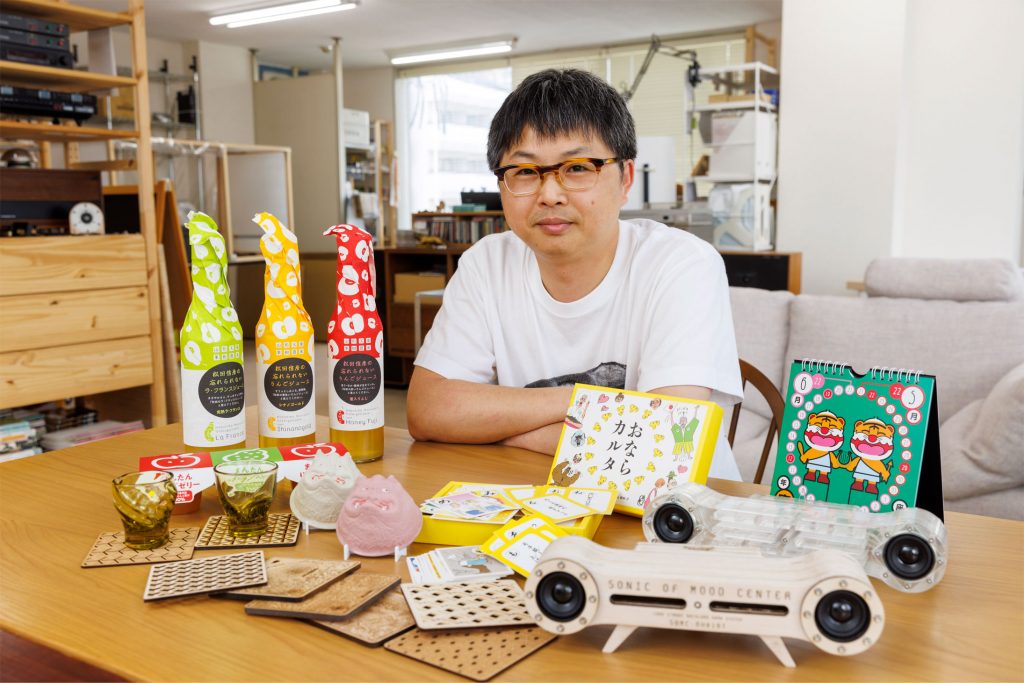丁寧な暮らし、ミツロウラップ
昨今、SDGsなどで注目を集めているのが、「使い捨てない商品」たち。
それは、女性用の布ナプキンであったり、繰り返し使えるカイロだったり、世の中は少しずつではありますが、「ものを大切に使うこと」にシフトしてきています。

写真:マメムギモリノナカのミツロウラップ。サイズは、S、M、Lとそろっています
そんな中、宮城県南部の小さな町で、「ミツロウラップ」を販売する会社を立ち上げた女性たちがいます。なぜ、ミツロウラップをつくろうと思ったのか。なぜ、丸森だったのか。
代表の山下久美さんに、お話を伺いました。
もともとは仙台で暮らし、セラピストとして活動していたという山下さん。「セラピストという職業柄、健康にとても興味があって。健康って、水、空気、食べ物がきれいでおいしいことにつながっているので、自然豊かな場所で暮らしたかったんです。なので、丸森町で起業したいというのが一番の思いでした。『地域とかかわりを持っていくにはどうしたらいいか』と考え、地域の素材を探していたところ、養蜂園さんが『蜜ろうが在庫になって使い道を探している』と聞き、ミツロウラップをつくろうと考えました」。

写真:「自分の暮らしも少しずつ丁寧になってきています」と、山下さん
丸森町の石塚養蜂園さんと出会った山下さんは、こんな思いを告げられました。「『養蜂園の蜜ろうは卸に出すと、みんな一緒になってしまう。自分の養蜂園の蜜ろうだと出口が分かる形で使ってほしい』。そんな風におっしゃっていました」。
こうしてミツロウラップをつくりはじめた山下さん。「今から3年前のことですが、当時はミツロウラップのレシピがなくて。やっと見つけたレシピでつくってみたけれど、思ったようにならなくて。蜜ろうを使ったラップと一言にいっても、レシピによって全然仕上がりは違うんですね。0.01gの調整をしながら、毎日試作を繰り返して、最初の販売にこぎつけました。今でも完成とは思わず、レシピを少しずつ改良しながらつくっているんですよ」。

写真:筒状になって販売されています
気を付けているのは、「使いやすさ」。
「どの程度、人の生活に浸透していくんだろうって思いながらつくっています。きっと珍しさから、手に取ってくださる方もいると思うんです。でも、それが使いづらかったりすると生活の一部にはなっていかないので」。
ミツロウラップは、1枚をヘビーユーズしない限り、半年から1年、ラップとして使用可能。「使った後は、やさしく手洗いして干してください。抗菌効果があって、野菜の保存などに力を発揮します」。長く使用して蜜ろうがはがれてきたら、“追い蜜ろう”を施して再生させるか、ふきんとして利用しましょう。そして、それがさらにボロボロになったなら、地面に埋めれば、土に還るそう。

写真:半分に切った小玉スイカをSサイズでくるむとこんな感じに
今、取り組んでいるのは、生活文化大学との産学連携による「竹染」の布を利用したミツロウラップづくり。「以前、丸森の竹で染めた生地のラップを販売していたことがあるんです。その生地は、地域の方に染めていただいていたので、なかなか安定供給が難しかったんですね。そこで、生活文化大学さんをご紹介いただき、産学連携で竹染を一緒にやらせてもらっています。それがうまくいけば、丸森の名産であるタケノコを育てるために伐採された竹を再利用することができます。タケノコという地域の名物を発信しつつ、地域素材の活用になったらいいなと思って、取り組んでいるんです」。

写真:サンドイッチをくるんだら、そのままお弁当として持っていきましょう。このサンドイッチには、「浜ののりマヨ」を使用しています
ひとつひとつのデザインもかわいらしい、マメムギモリノナカのミツロウラップ。
中には、亘理町の特定活動非営利法人「ポラリス」でのアート活動で、利用者の方が描いた絵をファブリックにしたもの。「宮城の方とご縁をつなぎながら、これからも丸森で、自分の生活を大切にしながら、がんばっていけたらなと思います」。

写真:「ポラリス」のデザインを施したミツロウラップ。包んでおいたラップがそのままお皿になるので便利!ランチタイムが楽しくなりそう
マメムギモリノナカのミツロウラップは、オンラインストアのほか、藤崎百貨店や東北スタンダードマーケットなど、仙台市内15店舗で購入が可能です。
ぜひ、あなたの生活の中にもミツロウラップを。その使い勝手の良さに、驚くことまちがいなしですよ。