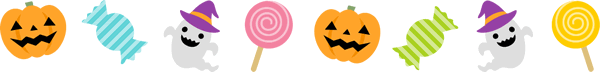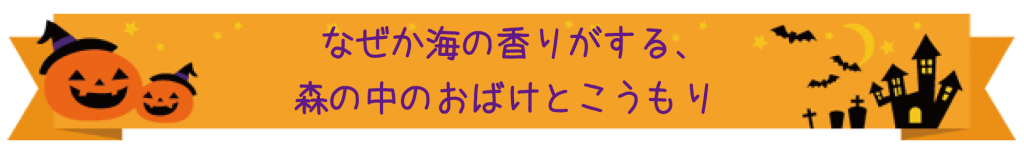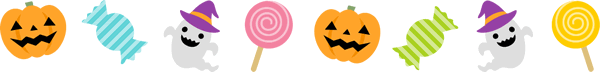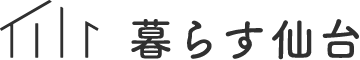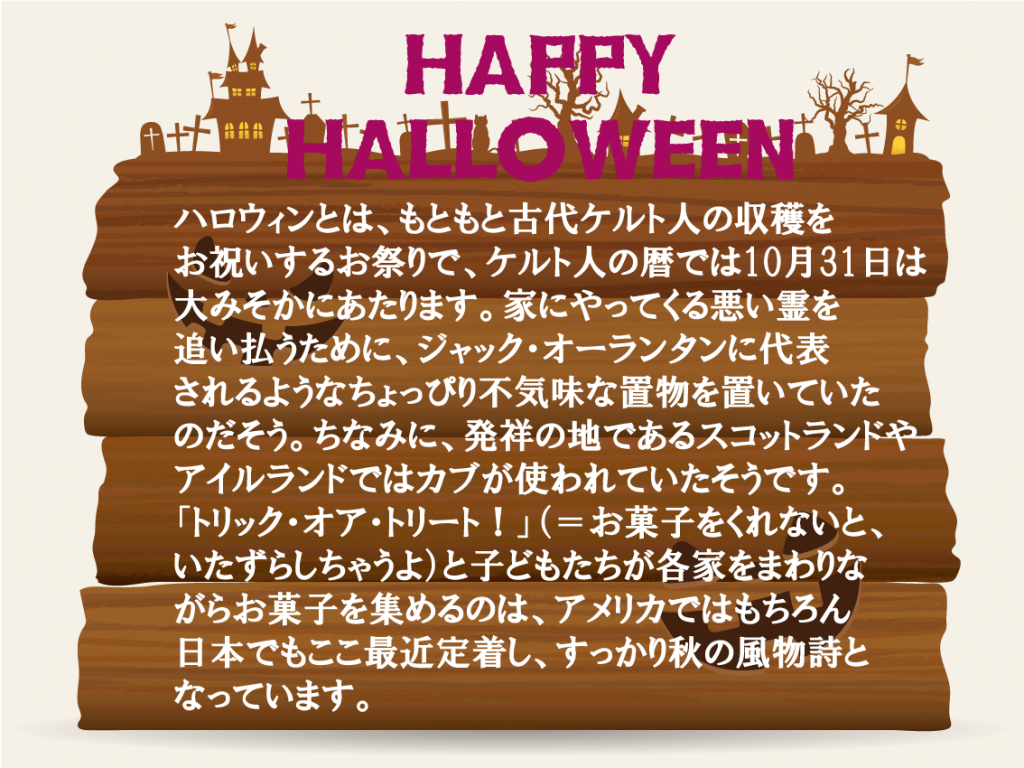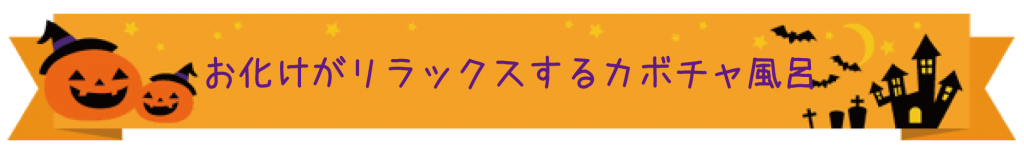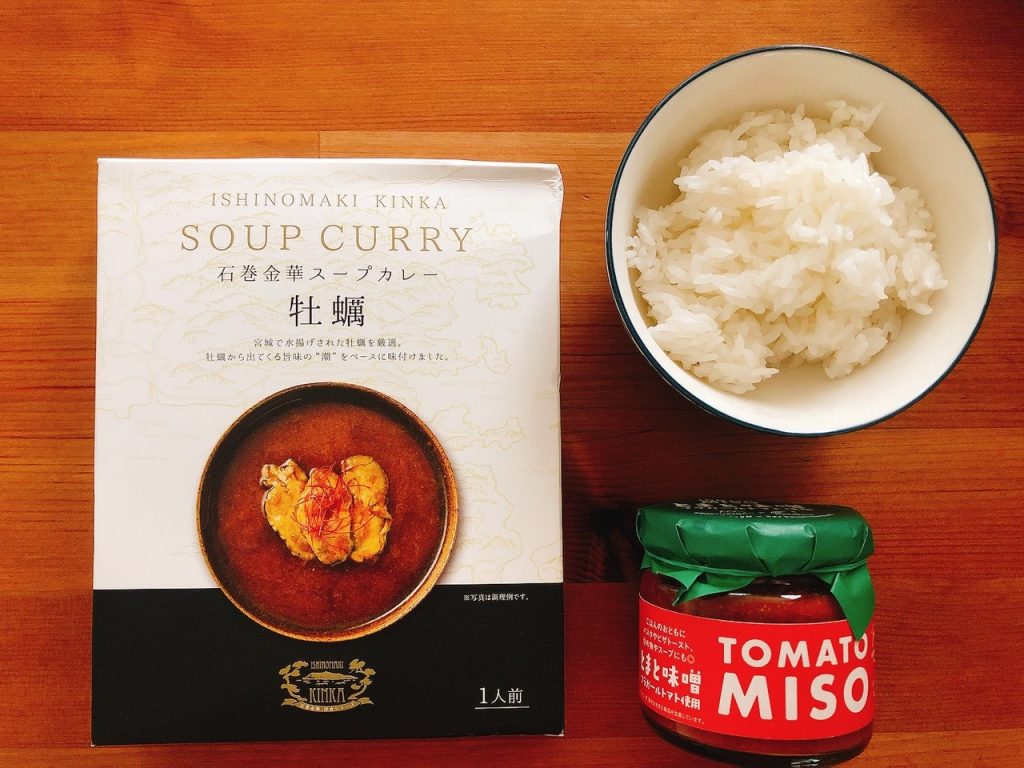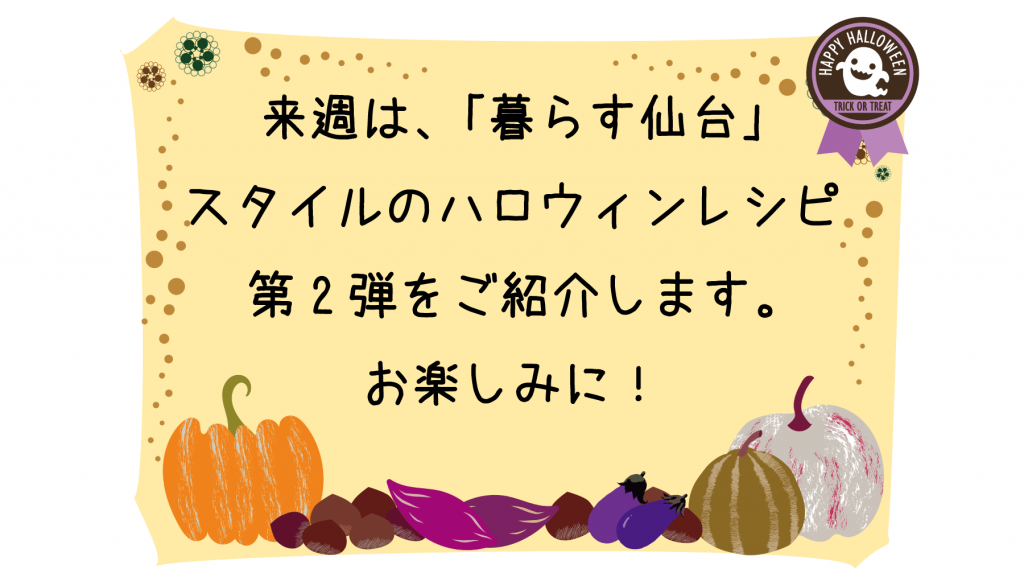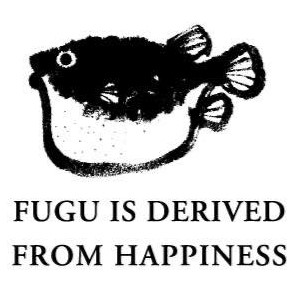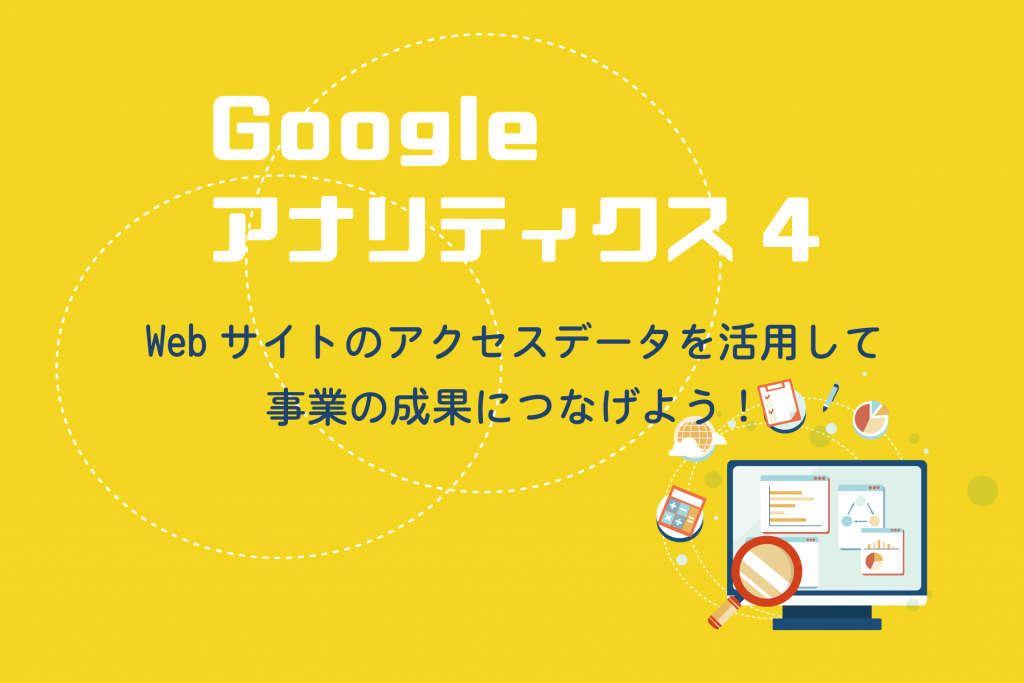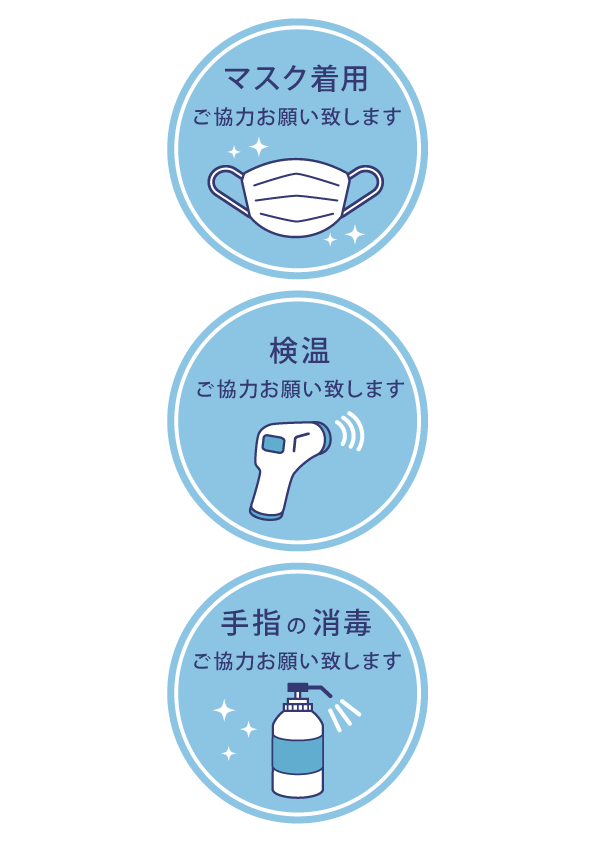アルファ電子株式会社は、仙台市産業振興事業団が主催する
第8回 新東北みやげコンテストの受賞企業です。
アイディア特別賞「う米めん」
福島県天栄村に本社を構えるアルファ電子株式会社。電子部品の製造販売を行うこの会社で、米粉を使った麺「う米めん」が誕生しました。なぜ電子部品の会社で、米粉麺なのでしょうか?
その誕生秘話を専務取締役である樽川千香子さんに伺いました。

写真:アルファ電子株式会社専務の樽川千香子さん。かわいらしい見た目に、最上級のパワーを秘めた女性です
取材にお邪魔したのは、同じ福島県内の郡山市にある日本大学工学部のキャンパス。ここにあるものづくりのための起業支援施設「インキュベーションセンター」で、樽川さんはものづくりのアイディアを生み出しているのです。
樽川さんは、「アルファ電子は祖父が創業者で、お客さまの計画に左右される業態です。ともすると、『来週の仕事がない』というようなこともあり、160人の従業員を抱える弊社では、このままでは立ち行かなくなるのが明白でした。父も医療機器やエネルギー事業への転換を図ってはいましたが、自社商品づくりをテーマに考えていこう、と。自社製品で、自社の努力で売れる商品をつくりたかったんです」。
最初に挑戦したのは、電子機器でした。しかし、大きな壁が立ちはだかります。「超音波で体を温める機械をつくろうとしました。クラファンで600万円ほど集まったのですが、製造に必要なのは3,000万だったんです。電子機器は、資金、人、技術、設備も必要で、本当に難しい。そこで、これまでの自分のご縁や努力でできる商品づくりに切り替えたんです。私は食べることが好きだし、女性、そして母であることを生かせないかと考えました」。

写真:樽川さんの努力の結晶である「う米めん」
そのときに、樽川さんの脳裏に浮かんだのは、東日本大震災の後、母子避難で身を寄せていた新潟県でお世話になったという方の顔でした。
「新しいことにチャレンジしたいというお話をしたら、『佐渡で、電子部品の会社が米粉の生産に取り組んでいるよ』と教えてくださって。すぐに現地に伺って、米粉の可能性に驚きました。米粉のパン、麺、スイーツなどを食べさせていただいて、まずそのおいしさに感動したんです。それで、すぐに福島に持ち帰って、父に相談して米粉商品の開発をスタートさせました」。
2019年夏、樽川さんの新たなチャレンジが始まりました。
「まず、佐渡から米粉を送ってもらって製麺を始めました。郡山にある製麺会社の試作室で成分表を見ながら、半年かけてなんとか形になったんです。資金は、厚生労働省の助成金を活用しました。なんとか形になったので、2020年に大阪の展示会に出店したんです。
かなりの評価をいただいたのですが、一つ問題がありまして。安心安全にこだわって添加物を入れていなかったので、賞味期限が3日と短くて。でも、私は賞味期限を長くするために食品添加物を入れて、『それを娘に食べさせられるか?』と聞かれたら、答えはNOでした。さらに、展示会でご一緒したある方に『これ、うまくないな』とはっきり言われてしまったんです。その方は『宮城県で、米粉とでんぷんだけで製麺をしている会社があるから、紹介する』とおっしゃっていただいて、宮城で製麺を行うことになりました」。

写真:白米中太麺は、うどんのようなツルっ、シコっとした食感が特徴。さらに、調理のしやすさも、台所に立つ人間にはうれしいもの。お出汁の風味豊かなつゆに、生姜とネギのシンプルなトッピングで素うどん風に
宮城県に製麺の拠点を移す際に、樽川さんはもう一つの決心をします。「『福島の企業がなぜ新潟の米粉?』とよく聞かれました。確かに、ご縁のあったところではありましたが、当時はまだまだ福島の食品に対する風評被害もあって。
でも、『やっぱり、福島から逃げずに福島のお米を使おう。おいしいものをつくろう』と決意したんです」。
よりおいしい麺にするために、樽川さんは工学院大学(東京都)の山田昌治教授の協力を仰ぎます。「教授は『麺の科学』という本を出している方で、『小麦の麺、パン、米粉のパンまでは研究したけれど、麺はまだないからやってみよう』とおっしゃってくださって。実際に食感の改良、香り、米の選定からいろいろ実験していただきました。
『う米めん』は2種類あるのですが、白い麺は『天のつぶ』という福島県のブランド米を使用した、うどんのような麺です。讃岐うどんと稲庭うどんの中間のコシを実現しました。茶色い麺は、『コシヒカリ』の焙煎した玄米を使用していて、コーヒーやアーモンドのような香ばしい香気が検知されています。生パスタやフィットチーネのようなもちもち感がある麺に仕上がりました」。
こうした食感や香気など、すべてを科学的データに拠ったのも、もともとが電子部品製造の会社であるがゆえ。「きちんと根拠をもって、なぜいいものができるのか。それがトレースできるのが大事だと考えています。理由があるからおいしいんですね。ただおいしいのではなく、なぜおいしいのかを私たちは、大事にしています」。

写真:玄米太麺は、「浜ののりだれ」と和えて「シーフードのりパスタ」にアレンジ。レモンとバジルで仕上げ、夏でもさっぱりの冷製パスタになりますよ
こうした科学的根拠に支えられ、極上の麺へと仕上がった「う米めん」は、仙台市産業振興事業団が主催する「新東北みやげコンテスト」でアイディア特別賞を受賞。「私たちの取り組みについて賞をいただいたことはあったのですが、商品自体が賞をいただけたのは初めてのことで。とてもうれしかったです」と、樽川さんは笑顔をのぞかせてました。
そして今年、2022年8月からは、工場を稼働させ、完全に自社での生産が可能になりました。
「事業再構築補助金が採択されて、福島のお米を使った米粉麺を福島で生産できることになりました。私たちは、ものづくりの会社で、自分たちでつくることを大事にしたいと考えています。ですので、この『う米めん』はもちろんですが、今後米粉麺をつくってみたいという人や企業さまのためのOEM(※)にも力を入れていきたいと思います」。
実際に、OEMについては農家や九州、山梨の企業から問い合わせがきているそうで、「地元のお米で麺をつくりたいと思っている方が、こんなにいるんだな、と。各地の地域商社のみなさんと組んで、各地のお米の麺をつくれたら楽しいですね」と、樽川さん。
※OEM=他社ブランドの製品を製造すること

写真:コチュジャン、酢、砂糖、しょうゆ少々を合わせてタレをつくり、ゆでた白米中太麺と和えれば、「う米ビビン麺」の完成!トッピングはきゅうり、ゆでたまご、キムチなどをどうぞ
さらに、この米粉麺の取り組みは、「コメ余り」という、日本の農家が抱える問題を解決する一助にもなりえるのです。
「私たちが麺をつくるためにお米を仕入れると、『新規需要米』として、農家さんは国から助成金がもらえるんです。その分、私たちは農家さんから安価に購入でき、また、『今年は何トンつくってくださいね』と契約するので、お米が余らないんです。そういう風な農家さんを増やしていければ、農家さんはお米が余ってしまうのではないか…という不安を持たずにお米を栽培できます。農商工の連携で、社会問題の解決にも役立てたらうれしいですよね。みんながそれぞれの立場で、得意なことをするのがいいんだと思うんです。この問題は、どこかだけが頑張ってもうまくいかないから」。
今後は、「3つのキーワード」で「う米めん」の販路を拡大していきたいと話す樽川さん。
「まずは『健康』をキーワードに、学校給食や病院食、会社の食堂の他、小麦アレルギーで悩まれている方々に向けて販路開拓していきたいです。ふたつ目は、『こだわり』をキーワードに『う米めん』を訴求し、輸出にも挑戦したいです。『コーシャ』というユダヤ教徒向けの、ハラールのような資格があるのですが、それを取得してイスラエルに輸出したいと考えています。最後は、『広げる』をキーワードに、先ほどお話したOEMで、日本各地の米粉麺をつくっていきたいです」。

写真:玄米太麺をカルボナーラに。モッチモチで、いつまでも食べていたいおいしさ!
おいしいお米を麺にして、日本全国、さらには世界の食卓を目指す-。樽川さんの挑戦はまだまだ始まったばかりです。
「よいもの」ページはコチラ
「う米めん」の生みの親である樽川さんのドラマチックな半生は
「Yahoo!JAPANニュース」でもご覧いただけます。
ぜひそちらもご覧ください。
取材/2022年7月
これまでの「銘品ものがたり」もご覧ください。